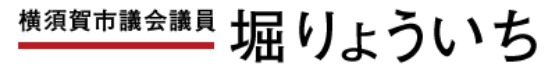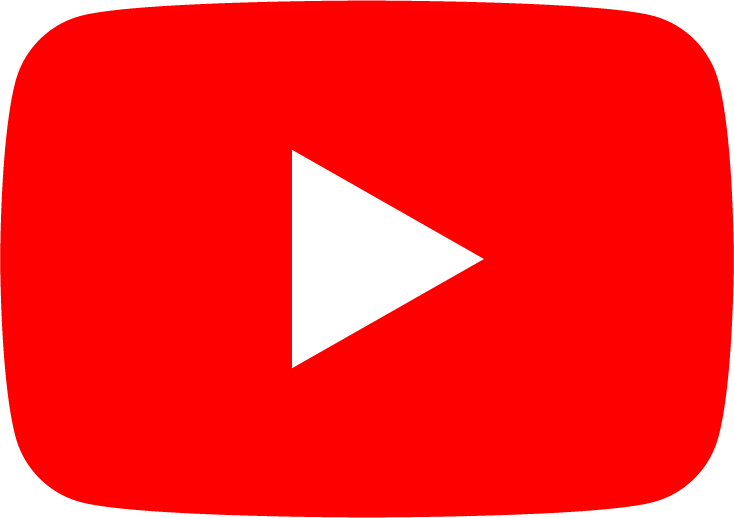おはようございます!横須賀市議会議員の堀りょういちです。
前回9月定例議会本会議での一般質問について「子どもの生活習慣の改善」をお伝えしました。
今回はもう一つの質問である「シニア世代の住環境を整備し 「住み心地の良いまち」へ」についてご報告します。
エレベーターのない古い5階建てマンションや谷戸地域など、高齢者が生活困難な家に住み続け、結果的に孤立や健康悪化につながる事例が増えています。
NPO法人の調査によると、男性約3割、女性約5割が現在の住まいに不満や不安があると回答しており、そこには段差や災害リスクなど安全面の問題が指摘されています。
中には家が広すぎるとか、家までの急な階段など、住まいの改修だけでは解決できない場合も多く、「住み慣れた場所」に固執することがかえって危険を招くケースもあります。
実際、高齢者の事故の7割以上が家の中で起きています。
こうした高齢者は日常的な外出が困難になり、結果として社会からの孤立や健康状態の悪化を招きます。
特に本市は谷戸地域をはじめ山坂の多い街であり、今後さらにこの課題は深刻化していくでしょう。
誰もが住み心地の良い横須賀を実現するために、訪問介護や搬送サービスの充実に加え、福祉と住宅政策を融合させた新たな取組みが必要ではないでしょうか。
そこで、私は以下の三点を提言し、市長から前向きな回答を得られました。
①自身の生活環境にあった早期の「住み替え」を支援するべき
2025年は団塊の世代が全て75歳になるなど、社会の高齢化はますます進展しており、それに伴って高齢者の住まい方も多様化しています。
「若い頃に購入した自宅に最期まで住み続ける」という旧来的なモデルから、高齢期に差し掛かり、将来を見据えてライフスタイルに合わせて住み替えることも珍しくなくなりました。
2011年に新設された高齢者向けの住まい「サービス付き高齢者向け住宅」は現在も戸数を伸ばしており、5年前と比較しても約3万戸増加していることから需要の高さが伺えます。
そこで、55-65歳の比較的若い層に対して、本人が元気なうちに住み替えすることの大切さやその方法について情報を発信する意識啓発を行い、併せて、市民からの住み替えに関する相談に対して積極的に応じ、住替え等のアドバイスや高齢者向け住宅・施設の情報提供ができる窓口の設置を民官連携で進めることを市長に提案しました。
市長からは、福祉部局と連携し、リーフレットやHP等で意識啓発を実施していく旨の答弁がありました。
一方、引越し費用などの経済的な補助制度の導入も提案しましたが、これについては見送られ、研究課題となりました。
これについては堀も引き続き言及をしていきます。
②老朽化マンションの実態把握を進め、管理計画の策定を積極的に支援する仕組みを作るべき。
本市において築 40 年を超えるマンションは44%を超えると推計され、防災面で課題のある建物も多くあります。
マンションの老朽化と並行して住民の高齢化も進む中、現在市は各マンションの実態調査を行なっています。
本市のマンション管理適正化推進計画では、マンションの管理者等に対する助言・指導等を必要に応じて進めるとしていますが、マンション管理者からの相談があったら対応するというような「待ち」の姿勢ではなく、民間事業者と連携して管理不全マンションに対して直接支援を行うなど積極的な支援を推進するべきではないでしょうか。
例えば京都市では「おせっかい型支援」と称して、市が「要支援マンション」と定義したマンションに対して、専門家や外部役員を派遣するなどの取組を民間事業者と連携して行っています。
そこで、支援の仕組みづくりを提案したわけですが、実態把握を進める中で担当部長からは「管理不全マンション」の定義を明確にし、そのマンションに積極的な支援を行なっていく旨の回答がありました。
③うわまち病院跡地の活用案の一つとして、多世代が集住する新たなモデルタウンを作ることを検討すべき。
最後に三点目は、元気な高齢者が住みやすい住環境を新たに整備することです。
要介護者を対象とした施設には元気な高齢者は入れませんし、一部のサービス付き高齢者向け住宅は介護施設のようになっているところもあります。
駅周辺のマンションなどは高齢の方が求めるようなサービスやコミュニティが少ないのが現状です。
高齢の方に適したハード・ソフトを備えた住宅の整備が重要です。
このような高齢者が暮らしやすい住環境の整備は全国的な課題となっています。
今年の6月に閣議決定した地方創生2.0基本構想では、「全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」(日本版CCRC)2.0の展開」が掲げられ、「3年後に、全国で100か所小規模・地域共生ホーム型CCRCの展開を目指す」としています。
CCRCは米国に普及する「健康時から介護時まで継続的なケアを提供する高齢者コミュニティ」のことであり、CCRC2.0は米国型とは異なり、高齢者だけではなく、多世代と障がい者一人ひとりが生きがいを持ち、個性と多様性を尊重する柔軟な共助のコミュニティを指しています。
また、大規模型だけではなく、小規模型でも推進するものとし、生涯学習×医療介護×産業創造×移動交通等を組み合わせた地域交流拠点づくりを推進しようと、現在国では省庁横断的な体制を構築し、制度改正等が検討されているところです。
現在、うわまち病院跡地の一部に看護系大学の設置が検討されていますが、残りの空間に高齢者向け住宅や学生寮、介護施設等を整備し、多世代が交流しつつ安全安心に暮らせるモデルタウンの設置を提案しました。
中長期の話であり、民間事業者との関係もある以上具体的な検討に入ってもらう段階ではないわけですが、市長には集住促進の重要性について理解をいただき、民官連携での可能性について言及をもらいました。
引き続き市と重ねてまいります。
=総括=
今回の質問は子どもと高齢者と、異なる世代を対象とした議論をさせてもらいましたが、共通しているのは部局の縦割りを越えた取り組みの必要性です。
子どもで言えば福祉部局と教育委員会、高齢者で言えば福祉部局と住生活担当の都市部。
社会課題が複雑化していく中で、このような横断的な課題はますます増えていくと思われます。
そうしたときに如何にこうした部局横断の課題に果敢に取り組み、制度の狭間に落ちる人をなくしていけるかということが、誰も一人にさせないまちの真髄ではないかと思います。
全部局のトップにいる市長がこうした課題に積極的に取組むよう、市全体に声をかけていってほしいと市長に伝えました。
市長からは「その通り」だと発言があり、想いは共通しているということがわかりました。
あとは実践あるのみです。行政が具体的にどのようなアクションをとってくれるか、チェックしてまいります。